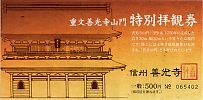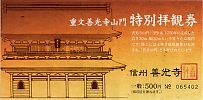善光寺
ぜんこうじ
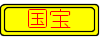
(本堂) |
| 長野県長野市元善町(もとよしちょう) |
| グーグルアース座標=N36 39 41.74 E138 11 15.78 |
 地図 地図 |
| 撮影日:2005/8/15 |
写真1:本堂(国宝)
 |
| 概要 |
- 日本の代表的な寺院で、どの宗派にも属していない。
- 天台宗大本山の大勧進(だいかんじん)と天台宗の寺院25院、浄土宗大本山の大本願(だいほんがん)と浄土宗の寺院14坊によって共同運営されている。
- 住職も天台宗の大勧進貫主(かんす)と浄土宗の大本願上人(しょうにん)が共同で務めている。
- 7世紀(飛鳥時代)に本田義光(よしみつ)が、本尊を自宅に安置したのが始まりといわれている。
- 数え年で7年に1度行われる「善光寺御開帳(ごかいちょう)」で前立本尊(まえだてほんぞん)を見ることができる。
- 本当の本尊は、インドから朝鮮の百済を経由して伝わったといわれれ、魂が宿っているため、公開されない絶対秘仏で、変わりに本尊の前に立ち、本尊の姿を写したと言われる前立本尊が公開される。
- 一つの光背の前に中央に如来、左右に菩薩が並ぶ、善光寺特有の「一光三尊像(いっこうさんぞんぞう)」と呼ばれる形式。
- 戦国時代に善光寺は川中島の戦で荒廃したため、武田信玄が1558年(永禄元)に本尊を甲府へ遷して、1565年に甲斐善光寺を建立した。
- その後、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らによって本尊が各地を転々とした。
- このことなどにより各地に善光寺がある。
- 本尊は1598年(慶長3)(安土桃山時代・江戸時代直前
- )に善光寺に戻された。
- 本堂:
- 十数回の焼失と再建を繰り返した。
- 現在の本堂は1707年(宝永4)(江戸時代中期)に再建されたもので国宝に指定されている。
- 本堂は木造建築として、東大寺大仏殿(奈良県奈良市)と三十三間堂(京都市東山区)に次いで大きい。
- 山門(三門)(さんもん):
- 「三門」は、「悟りを開くまでに通らなければならない三つの門」、とされる。
- 国の重要文化財。
- 2007年(平成19)に5年間かけた40年に一度の解体修理が完了した。
- 2008(平成20)年に内部の特別拝観が行われた。
- 鐘楼:
- 午前10時〜午後4時の毎正時にたたかれる。
- 長野オリンピックの際には開会を告げる音として全世界に響きわたった。
- 「日本の音風景100選」に選ばれている。
- びんずる廻し:
- 釈迦の入滅後、仏法を守るように命じられた十六羅漢(じゅうろくらかん)のひとり、賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)の像を、1月6日の夜に参詣者が福しゃもじでなでて無病息災を祈る行事。
- お戒檀巡り(おかいだんめぐり):
- 本堂の下をまわる完全にまっ暗な廊下を歩いて、手さぐりで本尊の真下にある錠前に触れると極楽往生ができると言われる。
- まっ暗な事に意味があるのに、赤ちゃんずれが、ぐずるので携帯電話の照明で照らしていた。最初はしょうがないなぁ、と思ったが、あまりにも必要以上に照らすので、文句を言った。それでもまだ、照らしているのだ。
- お朝事(おあさじ):
- 日の出とともに始まる法要。
- 一般も参拝できる。
- 夏は5:30から、冬は7:00(月日によって変動する)。
- お数珠頂戴(おじゅずちょうだい):
- 法要の前後にひざまずく人々に住職が数珠で頭をなでて功徳を授けられる。
- ことわざ「牛に引かれて善光寺まいり」:
- 昔、強欲なおばあさんが、干していた布を牛がひっかけていったので、追いかけていったら、善光寺に着き、信心を取り戻したというもの。→自分の予期しない思いがけないことで、いい方向にいく/本心ではなく他のことでたまたまよい事をする。
- 世界遺産への登録活動が行われている。
- 2008(平成20)年、長野冬季オリンピック10周年記念を合わせた、北京オリンピック聖火リレーが長野市で行われたが、善光寺は、そのスタート地点となっていた。
- 同時期に中国によるチベットの弾圧が行われていたため、同じ仏教徒としての憂慮と、参拝客の安全確保の意味から、スタート地点を辞退した。
- 理由は不明だが、辞退したことに対するものとも疑われる、本堂へのスプレーによる落書きがあった。
- 同年、辞退への感謝の印として、チベット亡命政府のダライ・ラマ14世より釈迦像が贈られ、また2010(平成22)年に本人が善光寺を訪れた。
- ミシュラン・グリーガイド・ジャポンで☆☆☆評価(「わざわざ訪れる価値がある観光地」 )。
|
- お戒檀巡り、史料館、経蔵などの共通券(本堂内の自動販売機):500円
|
 善光寺の記事 善光寺の記事 |
 行ったところ 行ったところ |
大勧進 |
| 大本願 |
| 善光寺史料館-p |
| 仁王門・仲見世周辺* |
| 歳時記 |
- 1/6:びんずる廻し
- -------8中:お盆縁日
|
| 公式HP |
| 善光寺 |