
- 石船の部分は乾隆帝時代の建造。
- 石船は池に面した堂干を起源とし、これらの水際の建築が石船に転化した。
- 1860年の英仏連合軍侵略の際に、上部の建物が焼失した。
- 西太后が再建するときに西洋式のものに変えた。
- 「河清海晏」からとった「清海晏」の名を付けた。
- 船体部分の4つの龍の口からは、楼閣の上で受けた雨水を吐き出す仕組みになっている。
- 内部には入れない。
写真11:清晏舫(石舫)(せいうんぼう/チンイェンファン(シーファン))
| その他のスポット | |||
| 諧趣園 | かいしゅえん | シエチュィユェン |
|
| 衆香界牌坊・智慧海無梁殿 | しゅうこうかいひぼう・ちそうかいむりょうでん | ヂョンシアンジエパイファン・ヂーホィハイウーリャンディエン |
|
| 宜芸館 | せんげいかん | イーイーグァン |
|
| 西堤 | せいてい | シーティー |
|
| 蘇州街 | スーヂョウジエ |
|
|
| 東堤 | とうてい | ドンディー |
|
| 銅牛 | トンニャオ |
|
|
| 東宮門 | ドンゴンメン |
|
|
| 徳和園(有料) | ダーハーユェン |
|
|
| 排雲殿 | パイユィンディエン |
|
|
| 排雲門 | パイユィンメン |
|
|
| 宝雲閣 | バオユィングー |
|
|
| Top|世界|省・自治区・特別市/中国|北京|市街地 | |||

写真11:清晏舫(石舫)(せいうんぼう/チンイェンファン(シーファン))

写真7:仏香閣(ぶっこうかく/フォーシアングー)(有料)
写真8 >>拡大
写真9:昆明湖(こんめいこ/クンミンフー) >>拡大
写真10:長廊 >>拡大
■全体図


写真2:「仁寿殿」( にんじゅでん/レンショウディエン)
写真12 >>拡大
写真2
写真8
写真11
写真10
写真9
写真7
写真6
写真5
写真4
写真1
■万寿山周辺図
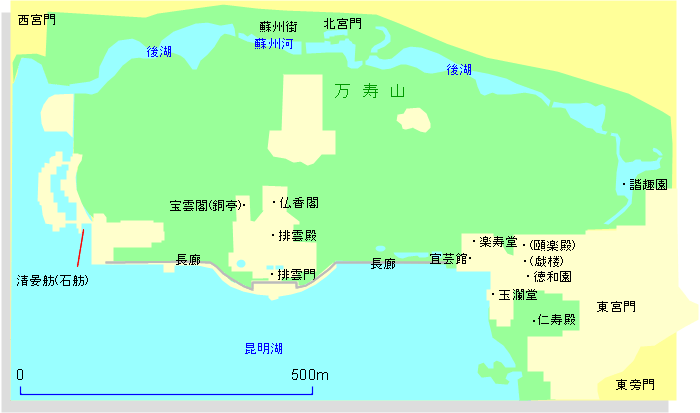

写真6:長廊(ちょうろう/チャンラン)
| 頤和園 いわえん イーハーユェン Summer Palace, an Imperial Garden |
| 撮影日:2004/9/11 |
写真1:仏香閣を望む |
| 概要 |
|