
写真2:八王子城跡入り口

写真3:路傍の石仏

写真4
- 橋台石垣のみ発掘されたものから、推定復元された
写真5:曳橋(ひきはし)


写真6:曳橋
- 敵に攻められたときには落とせる構造になっていたという
- 一部は400年間、土の中で崩れずに残っていた
写真7:石垣


写真2:八王子城跡入り口

写真3:路傍の石仏

写真4
写真5:曳橋(ひきはし)


写真6:曳橋
写真7:石垣

■東京都八王子市八王子城跡の情報、地図、概要


■記念スタンプ

写真8:城の入り口である「虎口」(こぐち)
写真9:御主殿跡 (360度) >>拡大
写真10:御主殿跡 >>拡大
写真12:八王子神社
写真11:本丸跡への道


写真13:山上からの眺め >>拡大
■広域地図
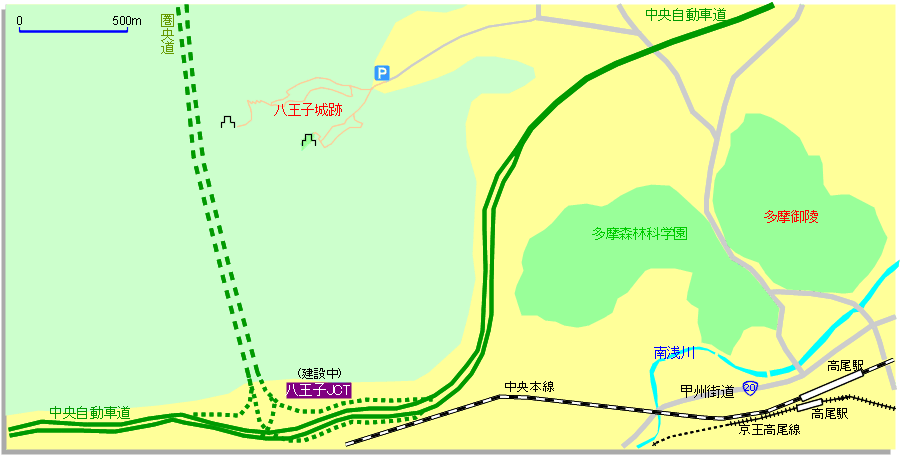
| 八王子城跡 (日本100名城) (国史跡) |
| 東京都八王子市元八王子町(もとはちおうじまち)3丁目 |
| グーグルアース座標(御主殿跡)=N35 39 12.41 E139 15 25.47 |
| 撮影日:2007/9/26 |
写真1:冠木門(かむりきもん) |
| 概要 |
|
| 関連HP |